
🌀「和」と「Inclusion」──事務所名に込めた理念
私たちの事務所名「和Inclusion(なごみインクルージョン)」には、日本的な調和の精神(和)と、誰もが共に生きる社会(Inclusion)という二つの価値を重ねています。
- 「和」は、争いを避け、違いを受け入れ、共に生きるという日本文化の根幹にある考え方です。
- 「Inclusion」は、国連の障害者権利条約にも明記されているように、すべての人が社会の一員として尊重され、排除されることなく参加できることを意味します。
この二つの言葉は、単なる理念ではなく、制度設計・行政手続き・社会参加のすべての場面で実現されるべき実践的な価値です。
🌿 私たちが目指す「和のインクルージョン」
和Inclusion行政書士事務所は、以下のような姿勢で業務に取り組んでいます:
- 制度の狭間にある声をすくい上げること 申請や制度利用において「見えにくい困難」を抱える方々に寄り添い、制度の壁を越える支援を行います。
- 共にある仕組みをつくること 障害の有無や国籍、年齢、家庭状況にかかわらず、誰もが「選べる」「参加できる」社会の実現を目指します。
- 「和」の視点で制度を翻訳すること 法律や制度の専門用語を、やさしく、わかりやすく伝えることで、誰もが理解し、活用できるようにします。
このように、「和」と「Inclusion」は、調和と包摂の両輪として、私たちの業務の根幹を成しています。

私のこれまで
〜警察官として、そして新たな道へ〜
私はこれまで、警察官として長年にわたり勤務してきました。刑事課長として事件捜査に携わったほか、県警本部の子ども・女性安全対策課では、課長補佐として企画業務を担当し、児童・障害者・高齢者に対する虐待対応、行方不明者対策、DV・ストーカー対策などに取り組んできました。
これらの現場で感じたのは、ひとつの機関だけでは解決できない複雑な課題が数多くあるということです。だからこそ、幅広い知識と、部内外を超えた連携がとても重要だと実感しました。
こうした気づきから、私は社会福祉や教育の知見を深めようと決意し、現在は通信制大学で学びながら、社会福祉士・精神保健福祉士・保健教諭・特別支援学校教諭の資格取得を目指しています。目指すのは「支援のプロ」としての総合力です。
学びのなかで出会ったのが「インクルージョン(包摂)」という考え方でした。障害のある人も高齢者も、子どもも外国人も、誰もが共に生きる社会。それは、福祉や教育の理想であるだけでなく、人口減少や地域の人材不足といった社会課題を乗り越えるための大切なキーワードでもあると感じています。
これからは、これまでの経験と学びを活かしながら、一人ひとりが尊重される社会づくりに貢献していきたいと思っています。どうぞ、よろしくお願いいたします。
現代の課題と、私が果たしたい役割
現在、福祉の現場では、生活に困窮している方、高齢者、障害のある方、そして外国人の方々など、さまざまな支援を必要とする人々が増えています。
こうした状況のなかで、行政と地域社会をつなぐ「中間支援機関」の不足が深刻な課題となっています。
特に問題となっているのが、制度申請や生活相談、成年後見、権利擁護などの分野において、「実務」と「福祉」をつなぐ専門的な支援者が不足しているという点です。
制度や書類の壁の前で立ち止まってしまう方々が少なくありません。
こうした現実を前に、私は「法律と福祉の橋渡し役」として、行政書士が果たすべき役割が大きいと感じています。
単に書類を作成するだけでなく、その人の生活背景や困りごとに寄り添い、制度を活用するための道筋をともに考える――そうした支援が今、求められているのです。
私はこれから、警察官・福祉・教育の現場で得た経験をもとに、制度にアクセスしにくい人々の“声”をすくい上げ、社会との接点を築いていく存在を目指していきます。

こんな行政書士を目指します。
私は、行政書士として、どのようなご相談にも真摯に対応できる“ゼネラリスト”を目指しています。
その根底には、これまでの経験と学びがあります。
まず、警察官として長年にわたり人々の安全と向き合ってきた経験から、「安心して相談できる対応力」を大切にしています。
そして、社会福祉として、ミクロ(個人)・メゾ(地域)・マクロ(制度)という多角的な視点から問題を捉え、柔軟な支援策を構築できる力を育んでいます。
また、精神保健福祉としては、心の問題に対して医療機関などと連携しながら、専門的な支援ができるよう努めています。
さらに、教育の分野では、子どもたちや保護者に対して寄り添い、必要な支援や指導を行える教育的な視点も大切にしています。
そして、行政書士としては、皆さまの権利を守り、複雑な制度や法手続きを分かりやすく丁寧にサポートすることを使命としています。
これらすべての視点を融合し、「安心・福祉・教育・法務」すべてを支えられる行政書士を目指してまいります。

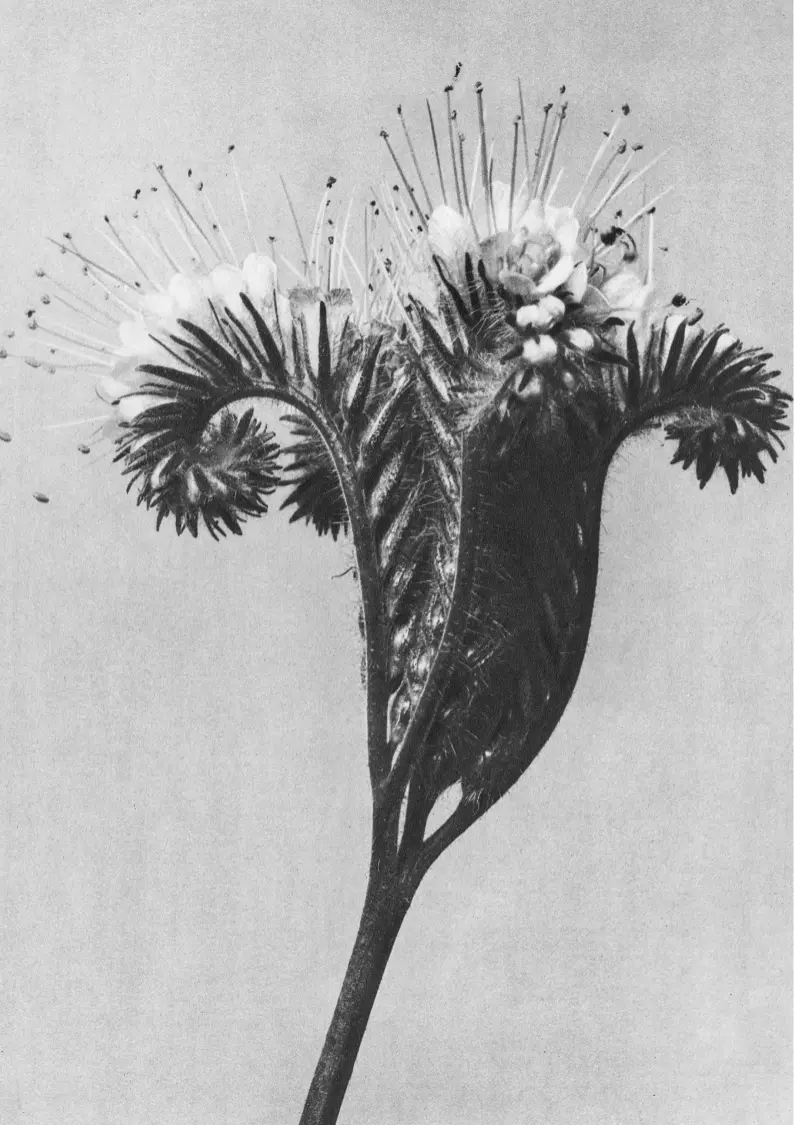
よくある質問と答え
Q1. どんな相談に対応していますか?
A.
当事務所では、以下のような幅広いご相談に対応しております。
成年後見制度の利用手続き
障害福祉サービスの申請や制度利用に関するご相談
外国人の在留資格申請や家族の呼び寄せ手続き
NPO法人や一般社団法人の設立支援
各種許認可申請や契約書の作成 など
Q2. 相談は予約が必要ですか?
A.
はい、ご相談は原則【完全予約制】とさせていただいております。
ご予約いただくことで、お一人おひとりのお話を十分に伺い、必要な資料のご案内や今後の見通しについて的確にご説明することができます。
お問合せメールからご予約いただけます。
Q3. 本人ではなく、家族や支援者が相談してもよいですか?
A.
もちろん可能です。ご本人が相談に来られない状況(病気・障害・ご高齢など)でも、ご家族や支援者の方が代理でご相談いただくことができます。
ただし、正式な手続きに入る場合は、必要に応じてご本人の意思確認や同意が必要となりますので、その点についても丁寧にサポートいたします。
Q4. 費用はどのくらいかかりますか?
A.
ご相談内容によって異なりますが、原則、予約制とさせていただき、メールによる初回相談は無料。以降、契約手続き以外の直接相談は、60分ごとに3,000円とさせていただいております。
各種申請や書類作成に関する報酬については、事前にお見積りを提示し、納得いただいてからの契約となりますのでご安心ください。
福祉関連の案件については、収入状況などを考慮した減額制度の対象となる場合もございます。
ご質問がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。
